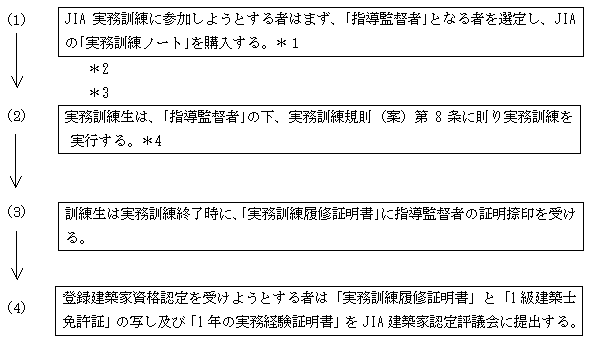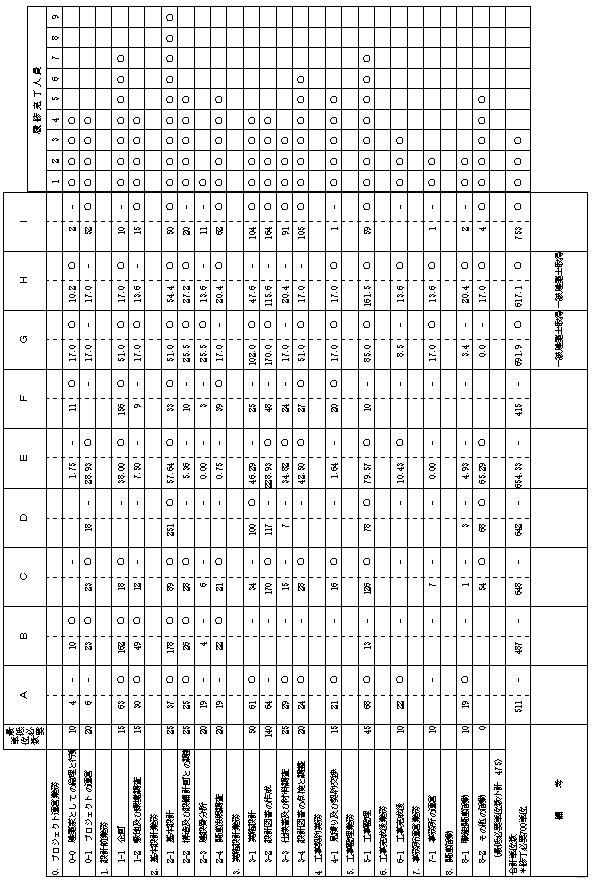1)実務訓練資格
UIA基準によれば専門的な建築教育は、その教育プログラムを承認された大学において、原則として5年以上の教育を受ける必要があります。従って、日本における現行の大学4年間の教育では不足であり、大学院2年間か、それに代わる専門教育機関により相当の教育が補足されなければ専門的な建築教育を修了したと認定されません。従って試行段階では専門教育が確立されるまでは、1級建築士資格試験の受験資格取得をもって、認定された専門教育を修了した卒業生と同等とします。
2)履修単位
1級建築士資格試験の受験資格者は、少なくとも3年にわたる一定水準を超える実務訓練を経た上で定められた科目の計700単位(必須科目475単位、選択科目235単位)の履修を完了し、さらに1年の実務経験をもって登録建築家資格認定受験が可能となります。なお、実務訓練期間中または実務訓練前に1級建築士に合格した訓練生は選択単位のうち100単位の履修が免除となります。
3)履修科目
訓練生は指導監督者のもと実務訓練を行います。
履修科目は「プロジェクト運営業務」「設計前業務」「基本設計業務」「実施設計業務」「工事契約業務」「監理業務」「工事完成後業務」「事務所運営業務」「関連活動」により構成されており、建築家として必要なすべての業務を網羅するものです。
上記科目の中で「プロジェクト運営業務」は「建築家としての倫理と行動」及び「プロジェクトの運営」、「設計前業務」は「企画」及び「敷地及び環境調査」、「基本設計業務」は「基本設計」「構造及び設備計画との調整」「建設費分析」「関連法規調査」、「実施設計業務」は「実施設計」「設計図書の作成」「仕様書及び材料調査」「設計図書の点検と調整」から成り立っています。
4)認定審査
認定審査は実務訓練後1年の実務経験を経て、JIA建築家認定評議会によって行われます。この認定評議会の審査を経て資格が認定され認定証の交付を受けることができます。この段階で1級建築士の資格を取得しているものは、直ちに登録の申請を行うことにより登録建築家となることができます。1級建築士の資格を取得していない者は資格の取得を待って登録の申請を行うことにより登録建築家となることができます。
図1・・・実務訓練のフロー図
| *1 |
試行期間中は実務訓練ノート購入時に実務訓練参加登録書の提出が必要。 |
| *2 |
実務訓練への参加資格は1級建築士試験受験資格を有するものとする。 |
| *3 |
指導監督者は、実務訓練参加者が所属する組織の上司で、登録建築家(試行期間中はJIA会員)とする。 |
| *4 |
第8条 実務訓練生は「実務訓練ノート」に示された事項を実行する。 |
| |
2 |
実務訓練の期間は3年以上とし、実務訓練履修科目700単位以上を取得しなければならない。なお、実務訓練期間中に1級建築士に合格した訓練生は選択単位のうち100単位の履修を免除する。 |
| |
3 |
訓練生は3ヶ月ごとに実務訓練の記録を指導監督者に提出し、その承認を受けるとともに、指導を受ける。 |
| |
4 |
訓練生は実務訓練に係わる記録、指導内容などを「実務訓練ノート」に記入する他、文書化して管理保管すること。 |
| |
5 |
訓練生及び指導監督者は、実務訓練評議会に対して、実行にあたっての疑問点などを相談できる。 |
表1・・・必須履修科目一覧
| |
最低必要単位数 |
| 0.プロジェクト運営業務 |
|
| 0-0 建築家としての倫理と行動 |
10 |
| 0-1 プロジェクトの運営 |
20 |
| 1.設計前業務 |
|
| 1-1 企画 |
15 |
| 1-2 敷地及び環境調査 |
15 |
| 2.基本設計業務 |
|
| 2-1 基本設計 |
25 |
| 2-2 構造及び設備計画との調整 |
25 |
| 2-3 建設費分析 |
20 |
| 2-4 関連法規調査 |
20 |
| 3.実施設計業務 |
|
| 3-1 実施設計 |
50 |
| 3-2 設計図書の作成 |
140 |
| 3-3 仕様書及び材料調査 |
25 |
| 3-4 設計図書の点検と調整 |
20 |
| 4.工事契約実務 |
|
| 4-1 見積り及び契約交渉 |
15 |
| 5.工事監理業務 |
|
| 5-1 工事監理 |
45 |
| 6.工事完成後業務 |
|
| 6-1 工事完成後 |
10 |
| 7.事務所運営業務 |
|
| 7-1 事務所の運営 |
10 |
| 8.関連活動 |
|
| 8-1 職能関連活動 |
10 |
| 8-2 その他の活動 |
0 |
| (最低必要単位数小計475) |
|
| 合計単位数 *修了必要700単位・1単位は7時間 |
5)モニタリング中間報告
実務訓練のモニタリングは2000年6月から実施され訓練生9名が参加しています。訓練生の所属はアトリエ事務所から組織設計事務所まで広範囲にあり、事務所の特性に左右されないようにしました。指導監督者は7名で、2名が複数の訓練生を指導しています。実務訓練の開始から2003年1月時点まで2年8ヶ月経った状況です。2003年1月時点での集計では必須単位の一部が未履修であるものの700単位相当を取得したものが3名おり、実務訓練の必要科目の履修は最短で3年程度で可能と思われます。それ以外の訓練生は400単位から650単位まで散らばっており、ばらつきが見られます。必須科目別に見てみると、「企画」「基本設計」「設計図書の点検と調整」「工事監理」の履修率が高く、特に「基本設計業務」のうちの「基本設計」は全員が履修済みとなっています。また、履修率が低い科目は「建設費分析」「仕様書及び材料調査」「工事完成後業務」「事務所の運営」「職能関連活動」となっています。その中で「基本設計業務」の中の「建設費分析」及び「事務所運営業務」は特に低調となっています。訓練生の中には、ほぼ企画基本設計段階のみを業務としている者や、現場監理を中心にしている者も見受けられ、指導監督者としての仕事の与え方やOJTのなかでの設計事務所としての教育の仕方なども今後の検討課題と思われます。また、訓練生及び指導監督者からのヒアリングによれば履修が困難な科目についてはスクーリング等による支援方策が有効との意見も、JIAとして今後検討を進める必要があります。
表2・・・モニタリング集計表
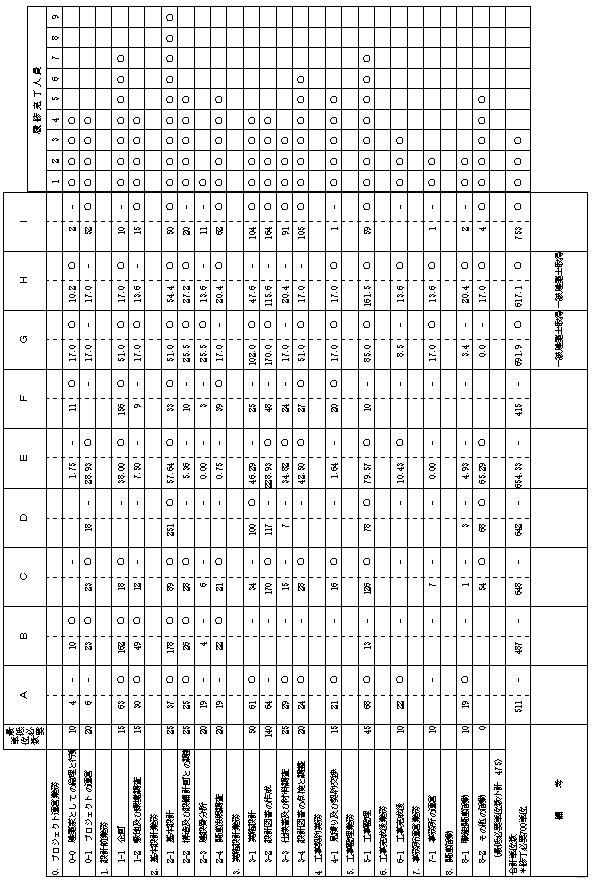 |
6)試行に向けて
実務訓練コースはUIA基準に則った方式であり、JIAとして是非共推進すべきコースです。今回は運用面の簡素化と、JIAの体制や財政面での負担を少なくすることを目指しました。
JIAの建築家資格制度推進委員会内の実務訓練分科会の役割は、1)実務訓練プログラムの作成及び改訂他、2)指導監督者及び実務訓練生の要請による相談への対応及びアドバイス業務、3)実務訓練履修科目のスクーリング、セミナーなどの計画立案に限定し実施する、の3点です。但し、試行期間中は訓練生及び指導監督者の把握も業務のひとつとします。
試行に当たっては訓練生の自主性と指導監督者の責任を尊重し、実務訓練履修証明は指導監督者が行います。指導監督者は本来であれば登録建築家であるべきですが、試行期間中はJIA会員と読み替え運用します。
実務訓練を有効に実施するためには訓練生の熱意だけでなく、訓練生への指導監督者の適切な業務配分、助言や理解が大切であり、指導監督者の役割が大きくなっています。訓練生の履修速度があまりにも遅い場合は、訓練生からの申し出により、実務訓練分科会が指導監督者に改善の提言をすることも必要になると思われます。
今後の課題としては先ず支部単位の運用が基本となる中で、支部の実施体制、スクーリングなどの具体的内容及びスケジュールの検討が必要となります。
またモニタリングの中でも、訓練生と指導監督員との人数上のアンバランスが指摘されており、指導監督者であるJIA会員が訓練生に間接的な指導しかできない場合も考えられるため、試行段階では、JIAが認定した準指導監督者による指導を認める必要も考えらます。
試行段階では立ち上げ期にあるため、実務訓練が広く普及し設計事務所ではどこでも行われているという雰囲気を作り上げていくことが大切です。
いずれにせよ、試行段階では上記のような課題を包含しつつ進むことになりますが、大切なことはモニタリング時、試行時を通してひとつの連続性を持たせ訓練生・指導監督者の多大な努力を尊重し、実を結ばせることにJIAは最大の、また細心の配慮を払いJIAへの信頼を確かなものとしていくことが肝要と思われます。 |